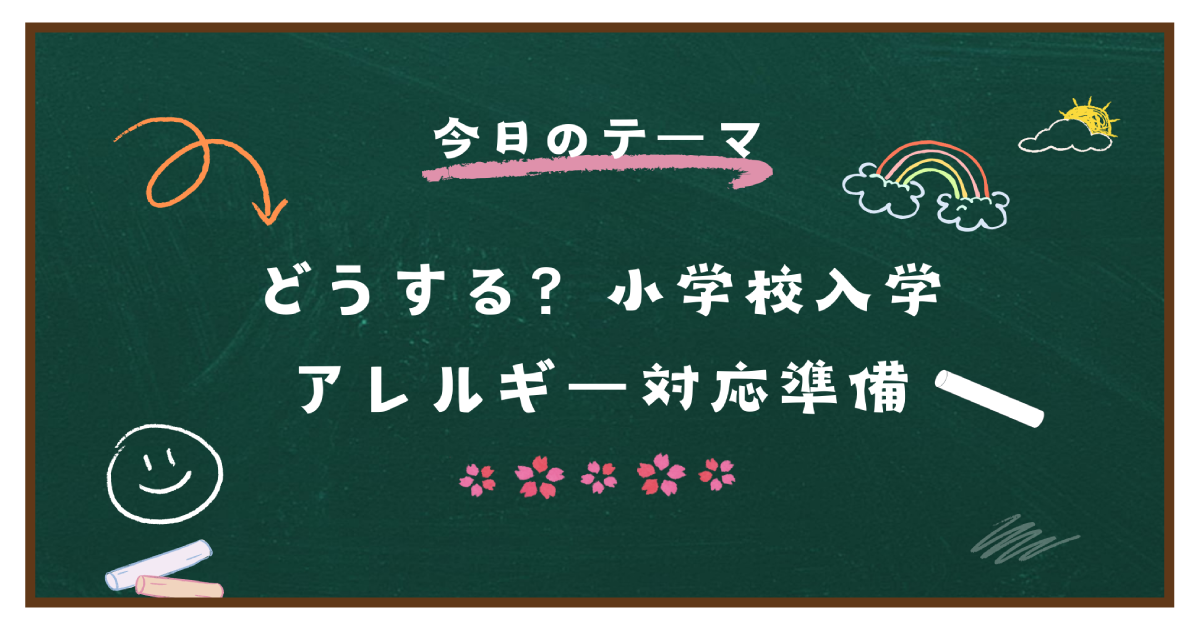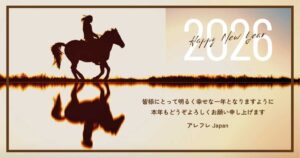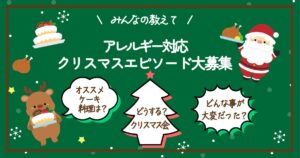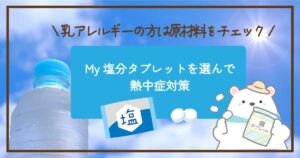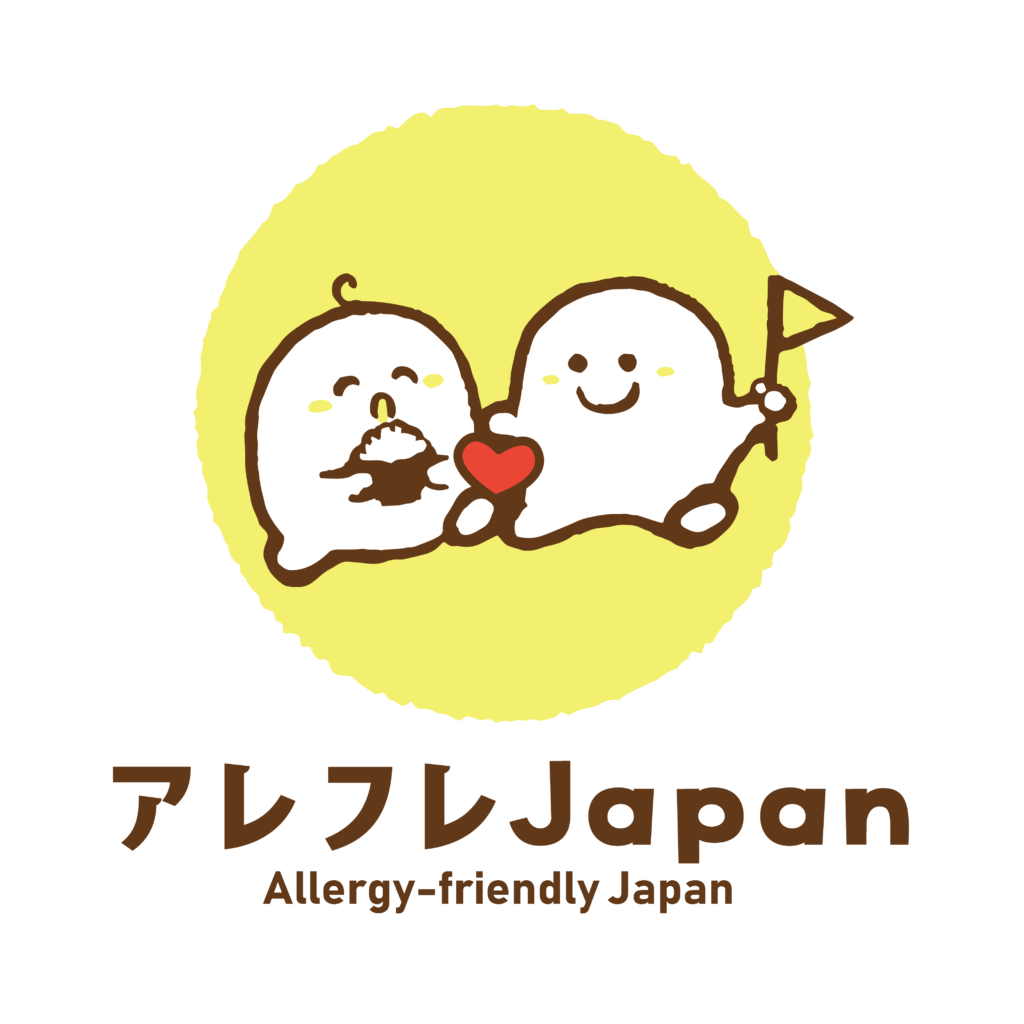この記事は、こんな悩みや疑問がある方へ
- 小学校入学に備えて、アレルギー対応をどうするか心配
- 具体的にどのような手続きをするのか流れを知りたい

もうすぐ小学校に入学、進級の時期がやってきますね。入学式に向けて、ピカピカのランドセル、通学バックに給食セットなど準備するものも沢山。どきどきわくわくした気持ちと同時に、新しい環境でのアレルギー対応に不安な気持ちもあるかもしれません。
そこで、この記事では入学にあたり学校とどのように連携していくのか、どのような準備が必要か、私の体験談を通してお伝えします。進級の際も、毎年確認が必要になりますので、合わせてご覧ください。
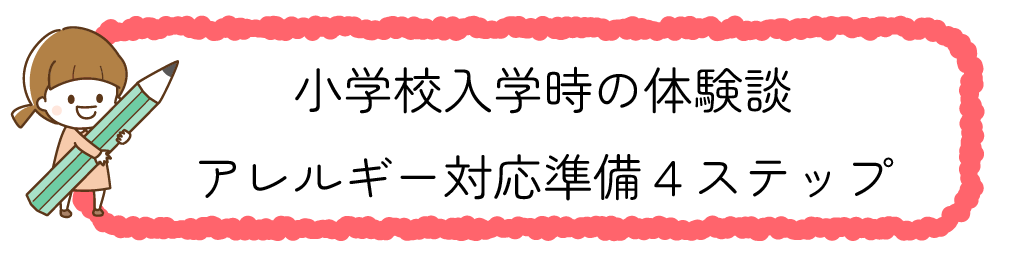
進学先により時期、実施内容が異なりますので詳細は、お住まいの市区町村や進学先の小学校にお問い合わせください。

アレルギー書類受取り
小学校入学する前年の10月~11月頃、学校で子供の健康診断が実施されました。案内の通知書は事前に郵送で送られてきます。
子供の小学校の場合、健康診断の最後にアレルギーがある方は個別に相談する時間がありました。子供のアレルギーのある食品、どれくらい食べられるか、などの簡単なヒアリングがあり、学校給食でどこまで対応できるか、など簡単に説明を受け、提出に必要な書類一式を受け取りました。
学校の給食が、食物アレルギーにどこまで対応可能か基準をしっかり聞いておくと安心です。
書類記入
「学校生活管理指導表」(両面)という書類を医師に記入してもらい小学校へ提出する必要があります。1月~2月頃までに病院を予約し、書類記入を依頼しました。子供と一緒に受診し、診断に基づいた最新の情報を記入していただくようにしましょう。
学校生活管理指導表(毎年提出)⇒病院の医師に記入を依頼
書式に従い、食物アレルギーの病型、アナフィラキシー病型、原因食物、除去根拠、緊急時に備えた処方箋、学校生活上の留意点詳細、緊急連絡先、医師名、医師機関名など記入してもらいます。最後に保護者の同意のサインを記入します。
書類は学校から配られますが、公益団体法人日本学校保健会のホームページからもダウンロード可能です。
食物アレルギー個別取組プラン⇒保護者で記入
書式に従い、原因食品と食べてしまった時の具体的な症状、対応手順、処方箋の内容と保管場所、アナフィラキシー発症状況、家庭における対応、主治医などの情報などを記入。
病院の予約が必要
この時期、病院は混雑します。予約がなかなか取れない場合があるので、早めに確認することをお勧めします。
アレルギー面談の日程調整
学校にすべての書類を提出、アレルギー面談の日程調整のためアンケートが配られ、候補日と時間を提出しました。
時間に余裕をもって記入
小学校への提出書類は大量にあり時間もかかるため、余裕をもって記入、提出しましょう。
校長、副校長、養護教諭、担任、栄養士が同席してアレルギー対応について話し合いました。
保護者からは、アレルギーがどのような時に起こるか、詳しい症状、アレルギーの薬や対応方法、給食時、学校生活で対応が必要なこと、クラスメートへの説明などについて話しました。
学校側からは、栄養士さんから給食時の対応について、担任の先生からは教室や日常生活での対応の擦り合わせなどを行いました。
今後の方針を話し合う大切な時間、対応をしっかり検討しよう!
私は校長室で、校長先生はじめ沢山の先生に囲まれ…緊張で声が震えました!短い時間になるので、質問事項やお願いしたい対応などをまとめて紙に書き持っていきました。
進級の時も、毎年STEP2からSTEP4までは同様に実施されます。2年生からは面談は希望制でした。ただ、この伝える努力はとても大切。担任の先生が変わり、アレルギーの子供を対応するのは初めて、という先生も多くいらっしゃいます。先生方もお忙しい中での対応となりますので、もし伝え足りない場合は、改めて時間を作ってもらいましょう。

学校とは別に、学童でも同様に書類提出とアレルギー面談が実施されました。学童では、おやつの時間があり、滞在する時間も長いのでこちらも対応が必要になります。
私の子供の学童の場合は、書類は以下3点でした。
①緊急時対応申出書⇒アレルギーについて、薬、緊急連絡先、主治医、緊急時の対応
②間食提供同意書⇒おやつの提供有無、提供方法(トレー、個人ボックスなど)
③間食提供食物リスト⇒食べていいおやつの商品名、製造会社などのリストを記入
おやつの商品名や製造会社のリストは意外と時間がかかりました。普段から食べているおやつをメモしておくと便利です。
学童では、初めての経験とのことで先生が特別な対応は難しいと戸惑われていたのですが、守るために最低限必要なこと(離れた席で食べるなど)、もしアレルギー症状が出てしまった時に対応をお願いしたいことをしっかりお伝えしました。
計画的に時間調整をして対応しよう!
病院の受診、学校での面談、学童での面談など、時間が必要になりますので、この時期、仕事は半休や時間休を利用して対応していました。事前に時間を確保しておく必要があります。
入学後も学校や学童との連携のため、コミュニケーションを大切に。
アレルギー対応は、どんな方にとっても精神的に緊張感を持たせてしまう事が多いかと思います。いつも感謝の気持ちを忘れずに、自分から必要な対応はしっかり伝える努力が必要と感じます。また、進級のたびに新しい先生、新しい環境に変わるため、先生の間で引継ぎしていたとしても、しっかり伝えることが日々の安心につながります。
以上、いかがでしたでしょうか。
準備の流れを確認することで少しでも安心に繋がればと思います。
入学、進級おめでとうございます!
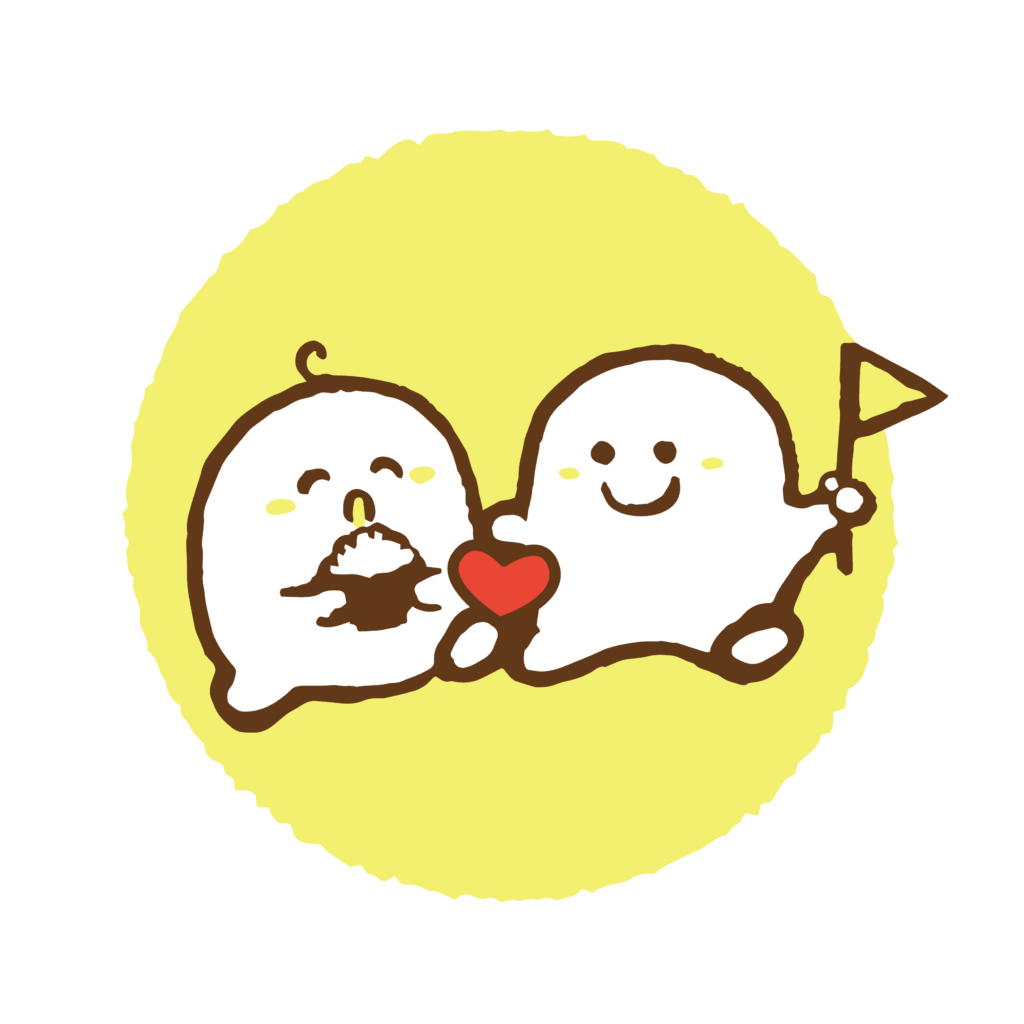
\ちょこっとリアルな体験談/

アレルギー対応は一人一人異なります。
ご参考までに、私の子供(卵・乳アレルギー)の場合の、アレルギー対応についてお伝えします。
<給食編>
・学校内で調理していたため除去食対応。毎月献立表を頂き栄養士さんと手紙で確認、除去食で対応するもの、代替食を家から持参する必要のあるもの(例えばパンの代わりにおにぎりなど)を確認します。
・給食のトレーは色が異なり、食べる時は先生の隣で食べます。
・牛乳パックを開いたり洗ったりする時間は、廊下で待ちます。
・学童も同様に、原則おやつリストから提供され、少し離れて食べます。
<学校生活編>
・クラスでアレルギーの事を先生から伝えてもらいました。この時、事前に子供に話していいかを確認しました。少しでも食べたり触ったりすると症状が出てしまうので、気を付けてほしいこと、好き嫌いとは違うことを伝えてもらいました。
・牛乳パックやプリンのカップなど図工の制作、家庭科の時間などに注意する。
<実際に症状が出たときは>
緊急連絡先に連絡をいただき、もし連絡がつかない時は薬を飲ませてほしいことを伝えました。
子供にも自分の身は自分で守れるよう何度も対応を確認しました。
しっかり準備して、学校で過ごす時間が安全で楽しい時間になりますように!
参考文献
公益財団法人 日本学校保健会公式ホームページ.2025
https://www.hokenkai.or.jp/index.html(参照2025-1-29)
学校保健 ポータルサイト.2025
https://www.gakkohoken.jp/(参照2025-1-29)